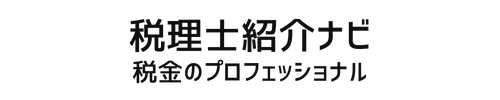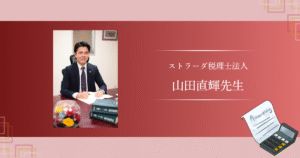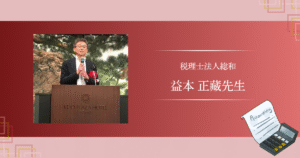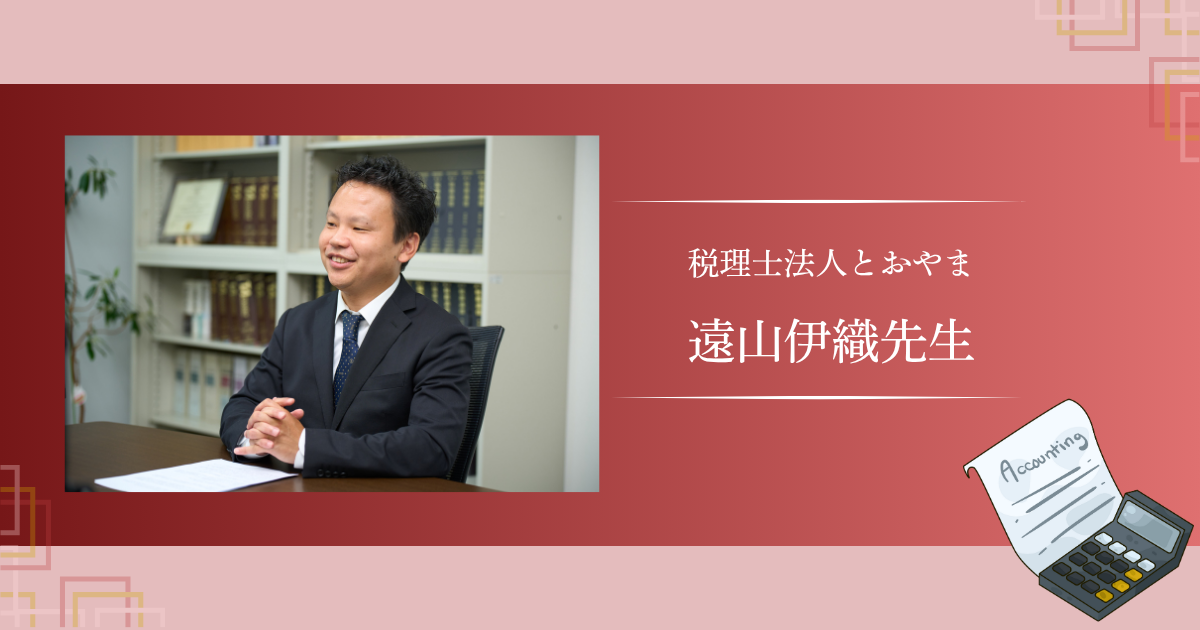この記事は9月11日に実施したインタビューをもとに作成しています。
先生のご出身と学生時代について教えていただけますか。
小野木先生:出身は埼玉県越谷市です。学生時代は大学の小説サークルに所属していて、私は会計担当を務めました。サークルでは毎年、自費出版で冊子を作っていたのですが、1冊600~700円とコストが高く、部員の負担が大きかったんです。そこで会計として見直しを進め、制作工程や印刷の発注方法を工夫してコストダウンを実現し、黒字に近い状態まで改善できました。みんなから「今年は負担が少なくてよかった」と喜ばれて、そこで初めて会計の面白さを実感しました。
執筆活動そのものも、現在の仕事に直結しています。税務のブログを書いたり、研修のテキストを作ったり、お客様とのやり取りで複雑な内容を文章でわかりやすく伝えたり、「言葉に落とし込む力」はサークルで鍛えられました。ちょうどSNS、特にツイッターが流行し始めた時期で、活動報告の発信が“バズる”こともあり、注目を集めることもありました。その結果、新入生の入部者数が例年の5倍ほどに増えた年もあって、情報発信の効果と難しさを肌で学べたのも大きかったですね。
税理士を目指されたきっかけは?
小野木先生:出発点は、先ほどのサークル会計の経験です。高コストな自費出版を見直して改善できたことで、会計の面白さに気づきました。商学部だったこともあり、まずは公認会計士を志して大手監査法人に入り、そこで大企業の監査に関わりました。印象的だったのは、上長が不在でも仕組みで会社が回る内部統制です。ダブルチェックをはじめとする統制手続きが組織に埋め込まれていて、個人に依存せずに誤りを防ぐ。こうした“システムとしての正確さ”を現場で見たことは、今の税務実務にも大きく活きています。
独立を決意された理由を教えてください。
小野木先生:監査法人での経験を経て、規模は小さめの税理士法人に移り、実務を通じて税務を深めました。そこで、所長が最前線でお客様対応をし、仮に誤りがあれば所長が謝る姿を見て、「自分のお客様を持ち、最後まで自分で責任を負いたい」と強く考えたんです。独立すれば、ミスがあればすべて自分の責任ですし、反対にお客様に喜んでいただけた成果も自分に返ってきます。その手触り感が、独立の一番の動機になりました。今振り返っても、決断してよかったと思っています。
仕事をする上で大切にしていることは?
小野木先生:最重要は“ミスをしないこと”。税務計算に誤りは許されません。そこで事務所では必ずダブルチェックを行います。私が確認して終わりではなく、従業員との相互確認を経て提出物を完成させる。どれだけ慣れていても、単独の視点だけでは見落としは起こります。複数の視点を通すプロセスを仕組みとして徹底する監査法人で学んだ内部統制の考え方を、日々の実務に根づかせています。
事務所の強みはどのような点でしょうか。
小野木先生:柔軟で自由度の高い働き方を実現している点です。税務は月末の申告・納付といった“明確な締め切り”があります。そこから逆算して作業計画を組めば、急な予定変更にも対応できます。社員の働きやすさを考えて、業務の品質を落とさずに柔軟に動ける体制を整えています。お客様とのコミュニケーションは、公式LINEやチャットワークを積極的に活用しています。相談や資料の受け渡しが簡単で、レスポンスも早くできるので、「すぐ反応がもらえる」「やり取りがラク」と評価いただくことが多いです。契約時には「年に何回かは対面でお会いする」お約束をしていますが、実際にはオンラインのやり取りで十分ご満足いただけるケースも増えています。お客様には本業に集中していただくための“使いやすい窓口づくり”を心がけています。
これまでで印象に残っているお手伝いの事例はありますか?
小野木先生:ご自身で申告された方から「不安なので確認してほしい」とご依頼を受けたことがありました。大きな誤りはなかったのですが、「本来は経費にできるのに入れていない」項目がいくつも見つかりました。そこを適切に反映した結果、前年より税額が下がって、とても喜んでいただけたんです。その延長で2~3名の方をご紹介いただきました。自己判断では“経費にできるか否か”の線引きが難しい場面が多々あります。専門家が基準に照らして一点ずつ確認するだけで、損失の回避やキャッシュの最適化につながる。その価値を実感した事例でした。
相続の節税やその他節税で実践的なアドバイスをお願いします。
小野木先生:相続は“早めのご相談”が何より大切です。亡くなられてから、あるいは直前にご相談をいただくこともありますが、その段階では取り得る選択肢が限られてしまいます。「まだ早いかな」と思う段階から税理士に相談していただければ、長いスパンで対策を組めますし、結果的に税負担の軽減につながるケースが多いです。事業者の節税策としては、小規模企業共済や経営セーフティ共済が代表例です。ただし、節税は“やり過ぎると資金が減る”側面もあるため、これから事業を大きくしたいのか、今は内部留保を厚くしたいのか、事業のフェーズに合わせてバランスを取ることが重要です。目的に沿って適切な打ち手を選ぶ、その設計段階から伴走するのが税理士の役割だと考えています。
良い税理士を選ぶポイントは?
小野木先生:コミュニケーションがしっかり取れることだと思います。税理士は資格業であり、知識水準の“最低ライン”は制度的に担保されています。だからこそ差が出るのは、質問に対して適切に、時には期待以上の形で答えられるかどうか。気軽に相談でき、意図を正確にくみ取り、必要十分な根拠を持って返してくれる相手を選ぶと安心です。
今後の展望について教えてください。
小野木先生:フリーランスや業務委託で働く方々への支援をより強化していきます。ご自身で申告される方の中には、本来計上できる経費を落とし切れておらず、結果として損をしてしまうケースが少なくありません。そうした方々に“もったいない”をなくして喜んでいただきたい、という思いがあります。また、大企業で長年働いた方が60歳や65歳を機に嘱託社員となり、収入が大きく下がるのを避けるため、業務委託に切り替えるケースも増えています。そういった方々は退職金や資産運用の課題も抱えやすいので、税務の側面から総合的にサポートしていきたいです。契約形態としては、スポットより顧問契約を中心に考えています。スポットだと、例えば個人事業主の確定申告で12月を過ぎてから着手する場合、「今年はこれを経費に」といった助言が間に合わないことがあります。顧問契約であれば、年間を通じて利益の推移を見ながら、「今のうちに対応したほうがよい」「この投資は時期をずらそう」といった提案が可能です。計画的に動ける分、結果的にお得になることが多いので、継続的な伴走で価値をお返ししていきたいと考えています。
 税理士紹介ナビ編集部
税理士紹介ナビ編集部最後に小野木先生の趣味についてお聞きしてみました。



小野木先生:ゲームがいちばんの趣味です。日中は税務で頭を使い続けるので、帰りの電車などではゲームでリフレッシュします。効率よく進める工夫が求められるタイプのゲームが多く、他のユーザーとの“勝負”になることもあります。その感覚は、業務や経営の効率化にも不思議と通じるところがあると感じています。それから、20年ほどペーパードライバーだったのですが、今ちょうど車を購入しようとしていて、これからはドライブも楽しみたいです。活動エリアは埼玉・東京が中心ですが、多摩や昭島など電車より車のほうが早い地域のお客様もいらっしゃいます。お客様先への訪問や急なご依頼にも機動的に動けるように、運転は“趣味兼実益”としてフル活用していくつもりです。
| 代表者名 | 小野木 康男 |
| 会社名 | ゆあ税理士事務所 |
| 会社URL | https://yuazeirishi.com/ |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2-25-2 ISC秋葉原6階 |
| 電話番号 | 0120-905-283 |